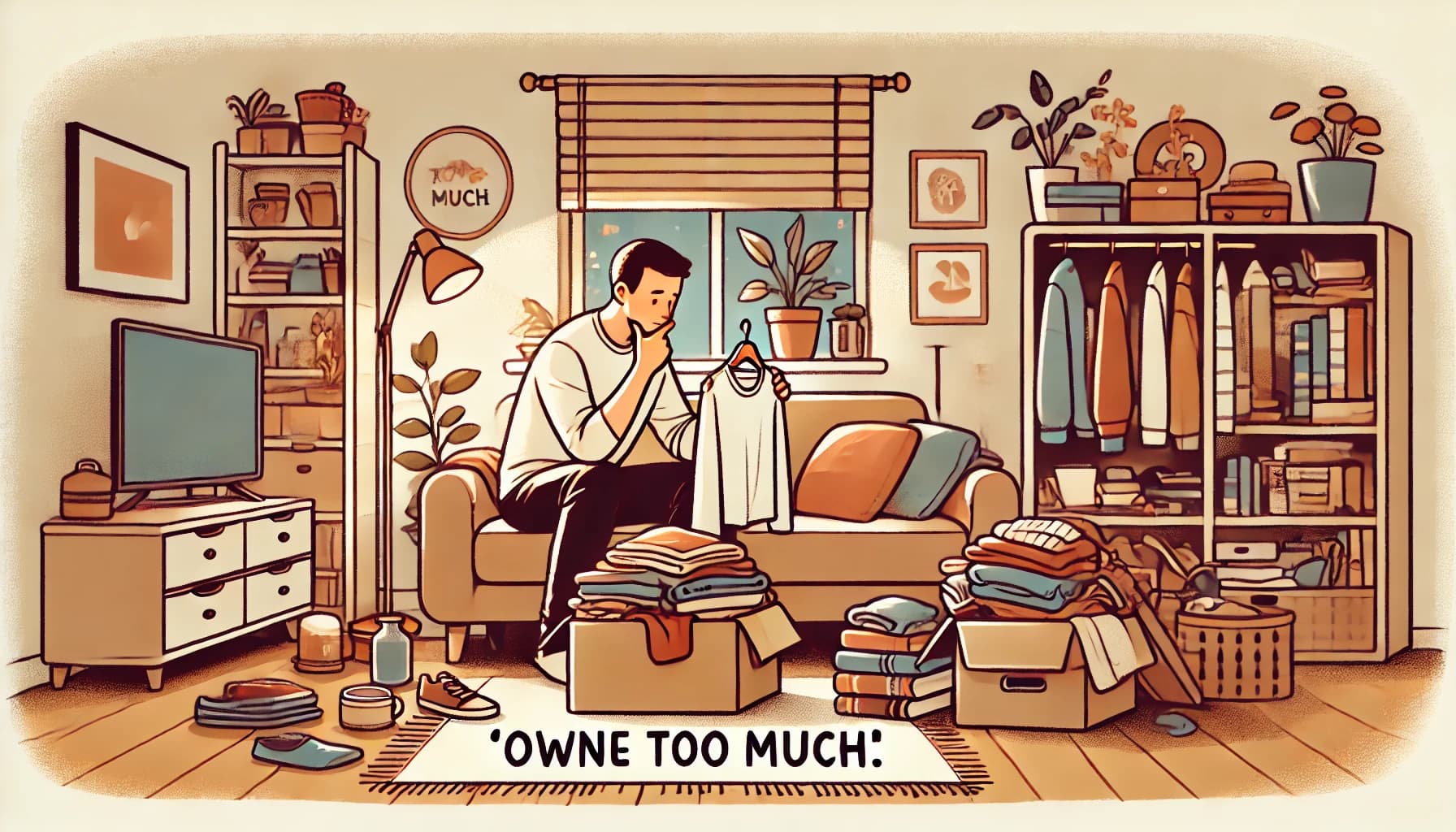片付けても片付けても、なぜかすぐに散らかってしまう…。 そんな悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか?
「収納グッズを増やしても、うまく片付かない」 「使いやすいはずの収納術でも、なんだかごちゃごちゃする」
そんなときは、そもそもモノを持ちすぎていないかを見直してみることが大切です。
この記事では、「持ちすぎチェック」を通して、片付けがラクになる考え方や手放しのヒントをご紹介します。
片付かない原因は“モノの量”にあるかも?
収納や片付けのテクニックに頼っても、うまくいかないことがあります。 その理由のひとつが、収納スペースに対してモノの量が多すぎること。
たとえば、洋服がクローゼットに収まりきらない、キッチンの引き出しがぎゅうぎゅうで出し入れしにくい…そんな状態は「持ちすぎ」が原因かもしれません。
「しまいきれない=片付かない」のは当然のこと。 収納術の前に、まずは“モノの量”を見直すことが大切です。
“持ちすぎチェック”をしてみよう
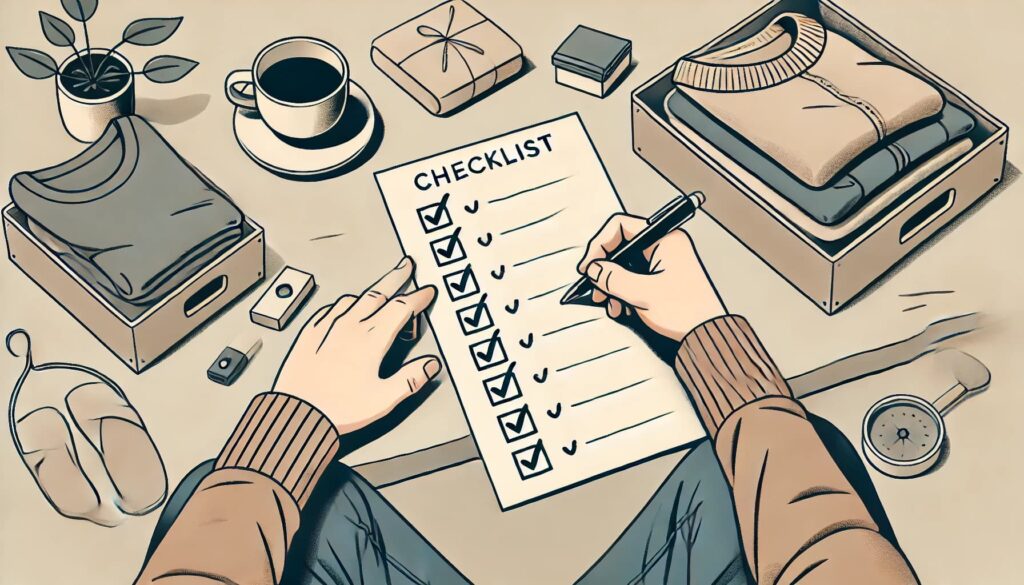
では、実際に「持ちすぎかも?」と感じたときに、どうやって判断すればよいのでしょうか。
✅ チェックポイント
☑ 1年以上使っていない
☑ 同じようなアイテムが複数ある(Tシャツが10枚以上など)
☑ 「高かったから」「もったいない」と思って手放せない
☑ 使いにくいのに、なんとなく置いてある
☑ 収納グッズがあふれてきた
☑ どこに何があるか分からないことが多い
☑ 片付けようとすると気が重くなる
☑ しまってあるモノを取り出すのに時間がかかる
☑ 新しい収納グッズを買ってもすぐいっぱいになる
当てはまる項目が多いほど、持ちすぎている可能性が高いかもしれません。
📦 アイテム別・適量の目安
| アイテム | 適量の目安 | チェックポイント |
|---|---|---|
| Tシャツ | 5〜7枚 | 洗濯サイクルで足りる数に絞る |
| パンツ | 3〜5枚 | よく着る・合うものだけ残す |
| 部屋着・パジャマ | 2セット | 洗い替えがあれば十分 |
| アウター | 2〜3枚 | 季節ごとにお気に入りを厳選 |
| 靴下 | 5〜7足 | 洗い替えを含めて必要最小限 |
| バッグ | 2〜3個 | よく使う+サブでOK |
| 帽子 | 1〜2個 | 季節や目的に合わせて選ぶ |
| お皿 | 人数×1〜2枚 | 出番の多い形を残す |
| 保存容器 | 3〜5個 | 重ねられる・シリーズ統一 |
| 調理器具 | 必要最小限 | たこ焼き器など使用頻度で判断 |
| フライパン・鍋 | 各1〜2個 | サイズ別でよく使うものを残す |
| ボールペン | 3本くらい | 書きやすいものだけに厳選 |
| ハサミ・カッター | 各1つ | 複数あるなら見直し対象 |
| ノート・メモ帳 | 1〜2冊 | 同時進行で使わないなら不要 |
| ケーブル類 | 必要な数だけ | 用途がわからないものは手放す |
これらはあくまで一例ですが、「適量ってこれくらいかも」と意識するだけでも、持ち物を見直すきっかけになります。
手放すのが難しいときの考え方

「使っていないけど、もったいなくて捨てられない…」 そんなときは、無理に手放そうとせずに、まずは次のような考え方を試してみてください。
- 「今の自分に必要か?」と問いかけてみる
- 思い出があるものは写真に残す
- メルカリ・リサイクルショップで売る・譲る
- 保留ボックスを作って、一時保管してみる
気持ちの整理がつかないうちに無理に処分すると、後悔してしまうこともあります。 “手放す”の前に、“見直す”というステップを踏むことで、より納得感のある整理ができます。
収納とモノの量はセットで考える
収納術だけに頼っていると、どうしても「とにかく収める」方向に考えが偏ってしまいがち。 でも本当は、収納は“持ち物の適量”が決まってこそ活きる仕組みです。
モノの量が適切なら、収納スペースにも余裕ができ、使いやすさもアップ。 「探し物に時間がかかる」「どこに何を置いたか忘れる」といったストレスも減っていきます。
収納と持ち物の量は、セットでバランスを取ることが大切なんです。
まとめ:ラクに片付く仕組みは「持ちすぎないこと」から
片付けに悩んでいるなら、まずは「今のモノの量が自分に合っているか?」を考えてみましょう。
必要なモノを適量だけ持ち、無理なく収められる仕組みをつくる。 それだけで、日々の片付けがグッとラクになり、暮らしにも余白が生まれます。
収納を増やす前に、“持ちすぎチェック”をして、 適量を知り、自分に合った暮らしの形を整える。
それが、無理なく続く片付け習慣の第一歩になります。
「なんで片付かないんだろう」と感じたときこそ、 “持ちすぎチェック”をきっかけに、心地よい暮らしを見直してみましょう。
「収納でなんとかしよう」と頑張ってきた人こそ、 “持ちすぎない”という新しい視点を、ぜひ取り入れてみてくださいね。